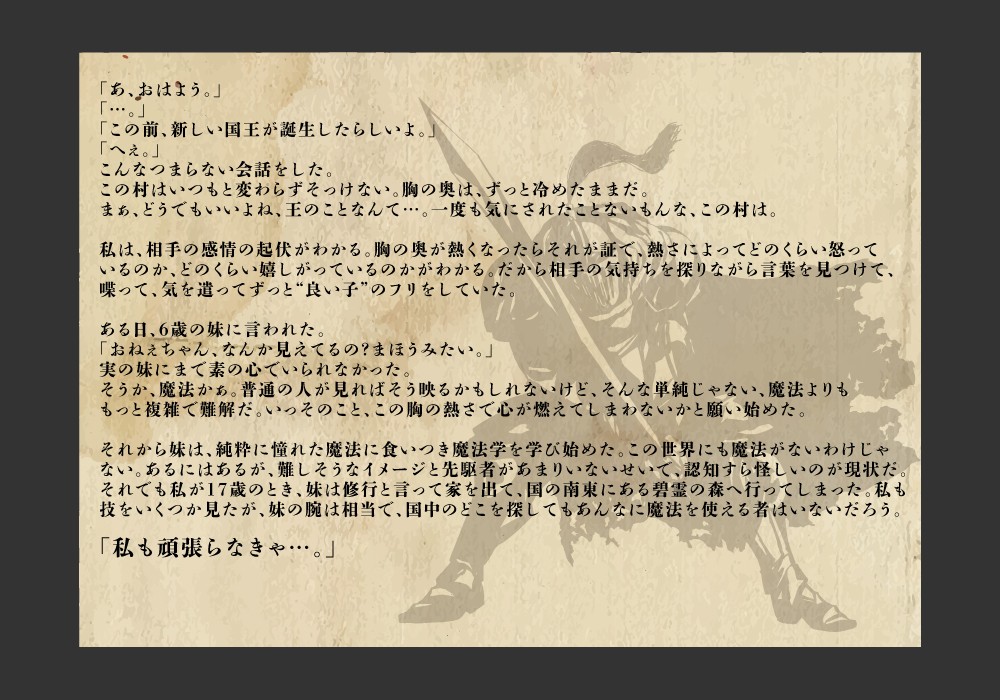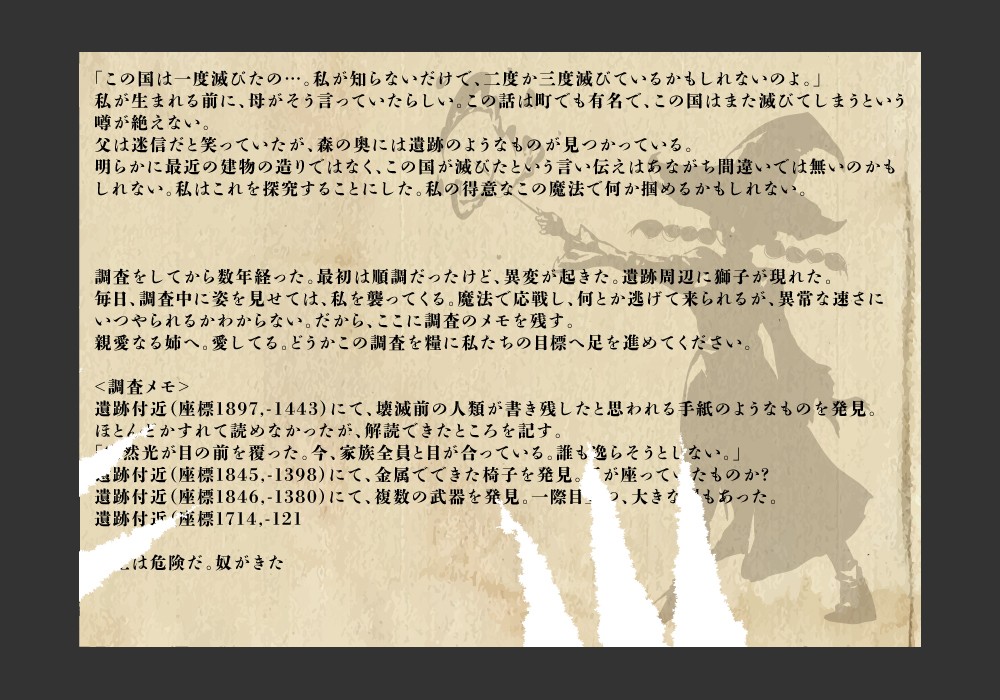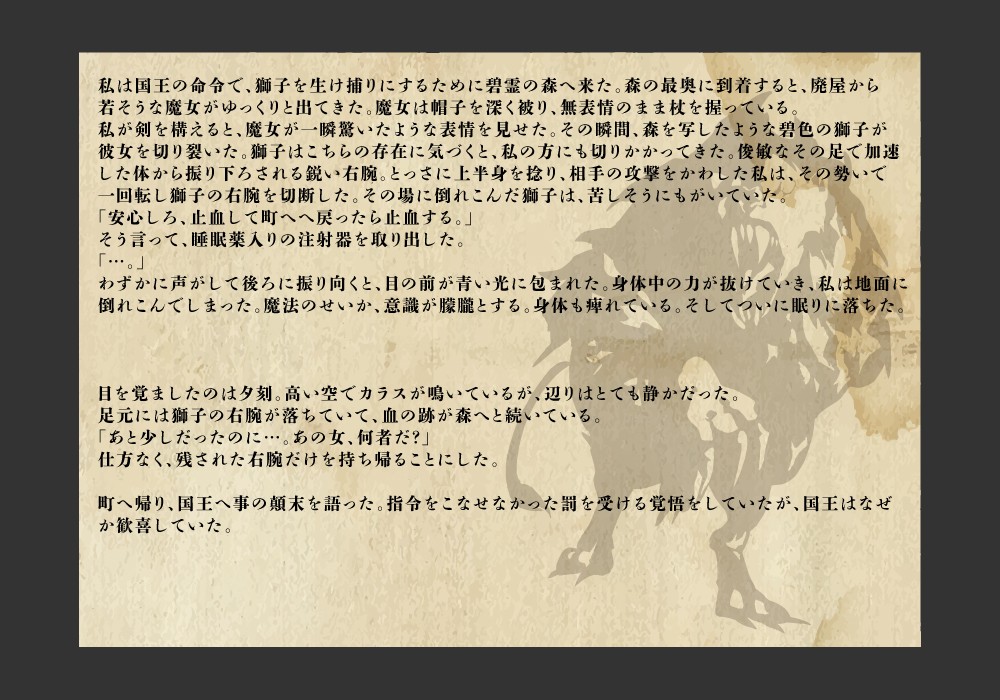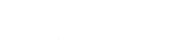Suiri/Sinriの世界
INTRODUCTION
私は、正体のわからない敵と戦っていた。
相手のことはよくわかっているつもりだった。
でも…、うまく掴めない…。霧のような、そんなハッキリしないものを相手にしていたんだ。
あぁ。よく考えればわかったのに。あんなに単純なのに!
けど…、過去の自分は今の結論には至らなかった。それが、私の死に際の後悔。
あなたになら出来る気がする…。そう信じて、この「物語」を託すわ。
第一話「五秘宝」
「壱億五秘宝。このおとぎ話はね、およそ一億もの秘宝について語られる伝説で、すごく長いお話らしいの。その中でも、位が一番上の"紅玉","水玉","碧玉"、あと"黄玉"と"紫玉"の五つは、この国のほとんどの人が知ってるお話なんだって。まだ二歳だった私に母が何度もお話を聞かせしてくれたわ。あなたにも聞かせてあげる。みんなかっこいい名前だけど、実は五つともお花なのっ…っよ!?」
家の外で轟音が響いた。王国では稀に戦が起こるらしいが、こんな小さな村には微塵も似合わない音だった。
「なに?いまの…」
妹は机の下にうずくまってしまった。
私は恐る恐る、近くの小窓から外をのぞいた。果てしなく続く水色の空と、もぬけの殻になった廃屋が見える。いつもと変わらない風景だった。
「ちょっと、外見てくる」
「こわいよ」
妹の心が灰色に染まった。
私は生まれつき人の心の色が見える。小さい頃は煙のような、もやもやしたものが胸のあたりに見えるだけだった。大きくなるにつれて色も形もはっきりとして、それが感情とリンクしていることを知った。
「大丈夫だよ、すぐ帰ってくるからここで少し待ってて」
不安そうな顔はまだぬぐえないが、小走りで玄関まで行き、扉をゆっくりと開けた。
いつもより少しだけ風が冷たい。
大きな音がした方に歩いていくと、地面に私の身長と同じぐらいのドーム型の穴が開いていた。
穴の中心には、空と同じ色の花が咲いている。爆発があったとは思えないほど、その花は凛としていた。
「勿忘草…?なんでこんなところに…」
私はその異様な光景に呆気にとられた。
「おねぇちゃん?」
突然後ろから声がした。妹の声だ。
「リン!なんで出てきたの!」
「おねぇちゃんが帰ってこないかとおもった」
妹は、わたしにしがみつき顔をうずめた。
「よしよし、怖かったね。一緒に帰ろう」
そのときなぜか身体中を寒気が襲った。
「…!おねぇちゃん!あの青いお花なに?」
「…あれはワスレナグサって言って、五秘宝の一つよ。」
「五秘宝?なんでこんなところにあるの?ばくはつのせい?」
「わからないけど、それしか考えられないよね…」
リンは勿忘草を見つめた。風に揺られながら、私たちは時間を忘れて花に見惚れた。
そいて変わった。花もリンも、そして私も。
「触らないで!!」
そう叫んだときにはリンは触れていた。青く美しき花、勿忘草はリンと共にどこかへ消えた。一瞬の出来事だった。一枚の葉だけがひらひらと空を舞い、地面へ落ちていく。
「リン…、噓でしょ?ねぇ!リン!!」
力が抜けていくのを感じた。ひざをついて、空を見た。上を向いても涙はこぼれていった。
空が真っ赤に染まるころ、ついに涙が枯れた。立ち上がり、穴を見た。花だ。空が照らしていた、その真っ赤な花はスイレンの形をしていた。いや、確かにスイレンだったが、川や池はここから少し遠い。水の上に咲くはずの花が、枯れもせずただ転がっているのは不自然だった。
「五秘宝…」
無意識につぶやいていた。そして、スイレンを手に取り走った。
五秘宝を全て集めたものは死ぬ。ただし、死ぬ直前の願いが一つだけ叶う。
「これが『一億五秘宝』の結末。過去に一度だけ、たった一度、死によって願いを叶えたものがいるらしいわ」
「あのときの私は、家に帰って支度をして、五秘宝を全て集めて、あなたを生き返らせることしか頭になかった。だけど良かったわ、五秘宝の結末をたどらなくて。家に帰ったら、なぜか怯えたままのあなたが泣いて『お帰り』って言うんだもの」
「おねぇちゃんだって涙を枯らして帰ってきたくせに!」
「そんなこと言っちゃうんだ!あれは悲しい夢を見たのよ、きっとそう」
あのときの思い出を二人で笑い合った。夢だったらいいと何回も願った。
「そういえば、おねぇちゃん。目、赤いよ?」
「あれ、充血かな?」
私は鏡を見なくても自分の目が赤いことに気づいていた。
だって、リンの目が青いから。
第二話「二人の父」
「じゃんけん、ぽん!」
あまりにも突然で、しかも4年前のあの日のことが書かれてあったのは衝撃だった。もう遅いよ、パパ。私たちは花に触れてしまった。花に触れて変化したのはこの目の色だけで、ほかに変わったことは無いし、これからも変わってほしくない。ただ、父は何か知っているようだった。私たちと花の関係性を。そして、リンがこの手紙の違和感に気づいた。
「あー、また負けたぁ。おねぇちゃん、じゃんけん強くない?」
「まぁね、あなたが出す手はだいたい予想がつくの」
「えー、なんかずるーい!」
心の若干の揺れで相手の心理が見えるのはまだ秘密。見えるとは言っても、実際何を出すかまではわからないからセーフ。見えることがずるいっていうのはかわらないけどね。
「で、これって何のじゃんけんだっけ?」
「え、もう忘れたの?さっき言ったでしょ、勝・っ・た・人が町までお肉を買いに行くって」
「勝った人って言った!?絶対言ってないでしょ!」
「言ったもーん、さ、買ってきて!しかも今日は4年に一度の私の2歳の誕生日なんだから」
今日は2月29日。今日は4年に一度しか訪れない特別な日らしい。誕生日は確かに特別だけど、なんでリンだけ4年に一度なのか全然わからなかった。リンの頭の中はどうなっているのだろう。それとも私だけが知らないだけ?町の方の人たちはみんな知っているのだろうか。
「リン、ここから町まで何分ぐらい?」
その質問にリンの目つきが変わった。
「ここから町までだいたい1.6㎞。おねぇちゃんの歩幅は60cmとして…。1歩が1秒だとすると2667秒かかるから、45分ぐらいだよ」
間違いない。答えが合ってるかもわからないけど、この子は天才だわ。
「あなた、まだ2歳でしょ?なんでそんなことわかるの」
「おねぇちゃん、冗談で言ってる?私はもう今日で8歳だよ。2歳っていうのは、29日で祝うとってこと!2歳のこんなしっかりした子いる?普通はまだハイハイでしょ。でもこんなにたくさんの知識を得られたのは、パパのおかげかなぁ」
私たちがこうして自由に暮らせているのも、父のおかげだった。父がこの家に置いていった財産で生活をしている。母はリンが生まれたあとすぐに亡くなった。父は、私が生まれたときにこの家から出ていった。「どこか遠くで探し物よ。すぐに帰ってくるわ」と母は言っていたが、私たち二人だけになっても帰っては来なかった。でもそれから5年後、今から2年前のある日、父から手紙が届いた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
娘たちへ
名前を先に決めておくべきだった。すまない、もうずっと会えそうにもない。顔もしらない他人のような父だが、この約束だけ守ってほしい。突然、目の前に綺麗な花が現れても決して触れないこと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「綺麗な花ってなんだろう、なんで、“娘たち”なのかな?ママは、おねぇちゃんが生まれたときにパパは出ていったって言ってたんでしょ?私が生まれたことをなんで知っているんだろう。そもそもなんでパパがいなかったのに私が生まれたの!?」
リンも私も混乱した。私は違う意味でついていけなかった。
そして今、その日のことを急に思い出した。・・・パパのおかげ?なんで?あのころのリンの言葉ではっと気づいた。父とリンは会ってすらいないのに、なんで“おかげ”になるのよ。
「リン!パパについて知ってることがあるの?」
「パパ?何も知らないよ?でも最近パパの部屋おかしいよ」
「パパの部屋?何かあるの?」
「うん、おねぇちゃん知らないかもしれないけど、実は本がたくさんあるんだよ」
「え?ただ真っ暗で殺風景な部屋じゃない」
わたしたちは毎日父の部屋の前を行き来する。埃っぽいその部屋をのぞいても何もないのは目で見て明らかだった。
「ちょっときて、見せてあげる」
言われるがままリンに引っ張られ、父の部屋の前まで来た。
「電気が通ってないのが残念だよね」
そういいながら、ずかずかと部屋の奥の本棚まで歩いていく。
「これね、そっから見ると何もないでしょ?こっち来て」
近づくにつれそれははっきりと輪郭を見せ始めた。部屋の入り口から見た本棚は空っぽだったのに、目の前の本棚には本がぎっしり詰まっていた。すべての本が黒に近い紺色で塗られていた。
「脳の錯覚だよ。ここには何もないと思ってしまったから、本が周りと同化したんだよ。」
リンは父が置いていったこの本を読んで知識を蓄えていたんだ。
「よく見つけたね…」
「実はね、本棚に何かが反射して光ってたの。あ!お金だ!と思って行ったらほんとに金貨だった」
「で、この本も運よく見つかったのね」
「そうそう!おねぇちゃん寝るの早いからさ、暇だから全部読んじゃったんだぁ」
この圧倒的知識に納得ができた。朝起きるのが遅いことにも。
「そういえば、この部屋の何がおかしいの?この本のことじゃないでしょ?」
「あー、えっとね、私の記憶力が正しければ、最近3日に1回ぐらいの頻度で本の位置が変わる」
今まで明るかった口調が心の色と共に冷たくなった。
「私以外の誰かがここにきて、本を触ってる」
「私たち以外の誰かが家に入ってるってこと!?」
「それはわかんない、おねちゃんかもしれないよ?」
「私は今知ったのよ!」
「冗談だって!」
そう言ってリンは笑った。心は暖かいオレンジ色に戻っていた。
リンの時折見せる冷たい雰囲気は、洒落にならないほど場を凍らせる。心の緩急もすごく、絶対に怒らせてはいけない一人だった。
「でもおねぇちゃんじゃなかったとしたらもっと怖いよ」
「確かに…」
「どうする?」
「夜、私が見張りをする。眠くならないように今から寝るね」
「え!お肉は!?」
「あ!そうだった!誕生日は祝わなきゃね」
その後、おねぇちゃんは5分で走って帰ってきたの。メロスより速いんじゃないかしら…。
第三話「見張り」
塩コショウで焼いた鶏肉をお皿に乗せ、フォークとナイフで一口サイズに切った後、1個ずつ丁寧に口へ運んでいく。この国ではお肉というもの自体が高級で、お金があっても普段こんなものは食べないから、特別な感じがして余計美味しく感じる。塩コショウっていう調味料は、遠い場所から運ばれてきたらしい。そう本に書いてあった。他にも調味料はたくさんあるらしいから、是非一度味わってみたい。
「おねぇちゃん」
「ん?なに?」
「もうちょっとゆっくり食べなよ」
「だって、美味しいし、早く寝ないといけないから」
そうだ。今日はパパの部屋の謎を解くために、交代で見張りをするんだ。
何かが侵入してくるとしても、こんな早い時間帯には来ないだろうけど、一応おねぇちゃんが寝てる間は私が家の様子を見ておこう。
「じゃぁ、先に寝るね。眠くなったら起こして、代わるから」
「わかった」
おねぇちゃんはパパの前の部屋のちょっと開けた場所で寝始めた。
私は、何をしよう。本は全部読んじゃったし、特にすることもないな。5週はしたけどもう一回読もうかな。
私はパパの部屋に行き、本棚を眺めた。昨日と位置は変わってない。と思ったが、いや実際に位置は変わっていないが、一番右下に本が一冊追加されていた。
「なにこれ…」
少し鼓動が速くなった。
「魔法学基礎?」
見たことのないジャンルだった。
後にわかったことだが、この国には魔法という概念が存在した。ただし、先駆者も資料も全くといっていいほど無いせいで、ほとんどの人が聞いたことすらなかった。
「魔法とは、潜在する気を外に解き放つことである…」
「ゆえに並大抵の精神力では体得は不可能である」
突然耳元で誰かがしゃべった。
「わぁっ!!!おねぇちゃん?」
「魔法の体得は始まりでもあり終わりでもある。」
そう言うと、おねぇちゃんは本棚をいじり始めた。
「まさか、本棚をいじってたのはおねぇちゃんなの!?」
「・・・」
「なんのため」
「この世界の」
「どういうこと?世界と本棚は関係ないでしょ!」
次の瞬間、本棚が音を立てて動き始めた。
「なにこれ…、どういうこと?」
「フフッ、やっとか」
奥には、下へ続く階段があった。
「私は君のパパの友人だ」
明らかにおねえちゃんの口調ではない話し方だった。
「この先は、私には行けない。自分の目で確かめてくれ。この世界のために」
そう言った瞬間、おねえちゃんの体は床に崩れ落ちた。
「おねぇちゃん!しっかりして!」
返事はなかったが、息はあった。ただぐっすり眠っているだけのようだった。
「ちょっと待っててね。・・・行ってくるから」
私は、真っ暗な階段を手探りで降りて行った。
第四話「開かずの扉」
私は、暗い階段を一つ一つゆっくりと降りていった。
ものの数秒で周りは明るさを帯びてきた。
「ランプがあるのね、よかった」
予想とは違った。ランプのように明るく光ってはいるものの、その灯りは宙に浮かんでいた。
「…」
日常とかけ離れた現象に言葉が詰まって出てこなかった。
目の前には、厳重そうな扉が一つ。錆びてはなさそうだが、私一人で開けられるか心配になる。
私はゆっくりと扉に触れ、押してみた。
「動く気がしない」
今度は全体重をかけて押してみた。
「なにこれっ!全然、動かない!」
扉は音一つすら立てなかった。
「鍵がいるのかな?」
そう思い、一旦階段を上がって、この家を調べてみることにした。
「こんな変な場所があるんだから、他にもきっとあるんだよね」
再び慎重な足取りで階段を上り、父の部屋まで戻ってきた。おねぇちゃんはぐっすりだ。
「どこから探索しよう」
探索と言ってもここは自分の家だ。怪しいところがわからない。そう考えていると、手に持っていた“魔法学基礎 ”という本が目に入った。
「そういえば、これなんなんだろう」
魔法という言葉すら初めて聞く。1ページ目をめくってみた。
「魔法とは、潜在する気を外に解き放つことである…。ゆえに並大抵の精神力では体得は不可能である。魔法の習得はまず空中に“電気”の塊を生み出すことから始まる。“水”、“火”、“氷” の塊、それらを全て可能にしたものを初めて“魔法使い ”と呼ぶ…」
「電気ってなんだろう」
知らない単語は気になって仕方がない。ページをペラペラとめくってみた。10ページを過ぎたあたりに様々な基礎魔法について詳しく書いてあるのを見つけ、おねぇちゃんが起きるまで夢中になって熟読し、演習を残すのみとなった。
「ふぁぁぁ、リン、おはよう」
「おねぇちゃんおはよう、よく寝れた?」
「うん、ぐっすり…、見張りは!?なんで起こしてくれなかったの!?」
「あぁ、おねぇちゃん気持ちよさそうに寝てたし、本読んでたら朝に…」
昨日の夜のことは覚えてなさそうだったので黙っておくことにした。
「なんで、私お父さんの部屋で寝てるんだろう」
「寝ぼけて、『見張り~ 』とか言ってこっちきたよ、すぐ寝たけど」
「え!本当?見ないでよ、恥ずかしい」
二人は笑いあったが、おねぇちゃんが思い出したように切り出した。
「結局誰も来なかったの?」
「あー、うん。勘だけど、もう誰も来ないし安心していいと思う」
「えー、それならいいんだけど…」
二人はしばらく沈黙し、お互いが目をそらした。
「…噓なんでしょ?誰も来なかったの」
おねぇちゃんは小さな声でつぶやいた。
「私ね、リンに黙っていることがあるの。嘘が…、なんとなく、わかるの…」
「それは黙ってたことなの?私だっておねぇちゃんがドギマギして挙動不審になったら、嘘ついてるのわかるよ?」
「違う!そうじゃないの!…え?私挙動不審なの!?」
「勘でとかじゃなくて、心の色が見えるの。不安だったり、悲しみ、喜びが色になって心に映し出されるの」
「どういうこと?心臓が透けてるの?」
「いや、心臓じゃないけど、そのあたりにもやもやがあって…そこだけは確かに透けて…」
「おねえちゃんの変態!」
「え、えぇ?そういう意味じゃないって!」
「わかってるって、でもそんなことがあるんだね」
「あまり驚かないんだね」
「それも普通なのかって思ってきたところ」
「どういうこと?」
「私もね、黙っていようかと思ったけど、本当は昨日襲われたの」
「え!?誰に?大丈夫なの?」
「おねえちゃん」
一瞬時間が止まったように無音になった。おねぇちゃんはすごくからかいがいがある。もっとからかっていたいが、さすがに可哀そうになってきた。
「うそうそ、襲われてないけど、おねえちゃんが関わっているのはほんと」
「すごく伝えづらいんだけど、おねえちゃんは体を乗っ取られてこっちの部屋に来たの」
「そして、本棚をいじってこの隠し扉を見つけた」
私は話しながら、本棚を動かし、さっき急いで隠した扉をもう一度開いた。
「嘘みたいな話、おねぇちゃんは何度も乗っ取られ、本棚の後ろの隠し扉を見つけるために個の本棚をいじっていたんだと思う」
おねぇちゃんは呆気に取られて、開いた口がふさがらないでいる。
「大丈夫、おねぇちゃん?」
「その…、乗っ取った人はなんのために…」
「なんでここに隠し扉があることを知ってたんだろう」
「それは、おねぇちゃんを乗っ取った人がパパの友達だからだと思う」
「パパの友達?」
「最後にそう言ってた」
「なんでパパは自分で帰ってこずにこんなことをするの」
「わからない」
おねぇちゃんは怒っているようだった。感情を表に出さないようにしているのがわかるぐらいに。
それもそうだった。自分の部屋なのに、帰らず、友人に娘の体を乗っ取らせるなんて正気じゃない。
まだしゃべらないほうがよかったかな。いやでもいつ話そうが許されることではないよね。
「おねぇちゃん、落ち着いて、必ず理由があるはず」
「理由?私たちに教えられない理由?手紙もお父さんの友達も!全部間接的じゃない!」
「なにが、起ころうとしているのかわからないわ!花もそう!」
「花?あの手紙のこと?」
「爆発音がして私が家の外に出たあの日、私はお父さんに触れるなと言われた綺麗な花に触れてるの…」
「え!?そうだったの?」
「もうあのころからおかしかった、家にいるはずのリンが急に目の前に現れて勿忘草に触れた」
「え、私ずっと家にいたよ?」
「そう、だからおかしいの。わたしは五秘宝スイレンに触れてしまった」
「もしかして私たちの目の色がおかしいのってそういうことなの?」
「色も触れた花と一緒だし、多分そうよ」
「…結構、私の中での謎が解けたわ、おねぇちゃんありがとう、私決めた」
「何を?」
「この一家は不自然なことが多すぎる。隠し扉の先、開かずの扉があるの。それを調べてママとパパの謎を解く」
「おそらくパパは生きてるけど、帰ってこられない状況にあるのよ。だから友達を使って私に調べろと言ったんだ」
「私も…、手伝うわ。この目の、花の謎を解きたい」
「でも開かずの扉なんてどうやって開けるの?」
「実はね、“魔法 ”が使えることが今わかったの」
リンの手からは微かに雷のような光が走っていた。
残された手記